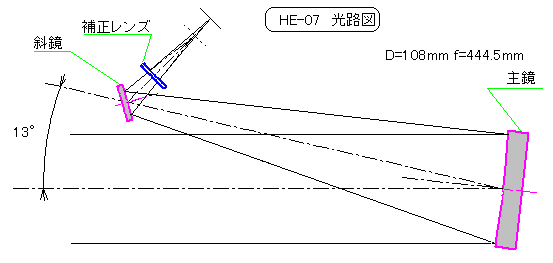
実用性は?だが、対空型のレイアウトとし、人間工学シリーズの機種番号 HE-07を付与した。
前回の記事から既に1年以上経ってしまったが、再開。
この望遠鏡は、実験機であるが、一応目標を立てた
・接眼部を45度に傾斜させたハーシェル・ニュートン式の変形タイプとする。(対空型とするため)
・短焦点によるコマ収差の補正用としてバーローレンズを入れる
・倍率30倍程度のRFTとする。
ハーシェル・ニュートン式とは、日本の望遠鏡製作の草分けである中村要氏が昭和初期に考案したもの。
光軸ズレが目立たない領域〜口径8cm以下、F10以上の長焦点〜で実用になり、商品化もされていたという。
今回使用を考えている手持ちの鏡は
10cm F4という超短焦点であり、ハーシェル・ニュートン式には全く不向きなスペックである。
無理を承知で光路図を作ってみた。
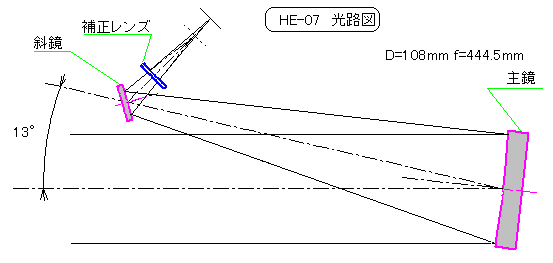
実際に書いてみると、光束が折り重なっているため、あまり自由度は無く、斜鏡、補正レンズの配置はこの図のようにならざるを得ない。
主鏡の傾きは実に6.5度にもなり、そのままでは凄まじく流れた像になるだろう。
補正レンズには、この流れた像をキャンセルする働きが絶対に必要になる。
前回PART2の検討では、ここを乱視レンズで置き換えることは現実的ではないことが分かった。
以前、仕事であるカメラ会社のお偉方に同行し、出張先の写真を撮ることになった。(写真の腕はゼロなのに・・・)
カメラはその役員が使用しているものをお借りした。
現像してみると、あまりに良く写っているので驚いた。自分のカメラとは別格の写りであった。
そのカメラ会社の知人に「あのカメラが気に入ったので買いたいのだが」と言うと、考え直せという。
なぜならば、それは念入りに調整された「重役向けバージョン」に違いないからだ、という。
さて、ここで疑問になってくるのは、その調整とは何かである。
天体望遠鏡ならば、光軸修正装置がついている。
しかし、カメラや双眼鏡のレンズは、枠の中にがっちりと固定されれており、調整機構などはない。
各部が完璧に出来ていれば、これでも問題は無いだろう。
実際の光学機器の工場では、コリメーターで作られる人工星や解像チャートでテストされる。
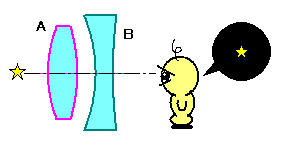
レンズや枠は、多かれ少なかれ製作誤差があり、実際の見え味は、設計値よりは劣る。
たとえば、下図のように あるレンズ(B)が何らか原因で傾いていると、像に「フレア」と呼ばれる不快な尾が発生する。
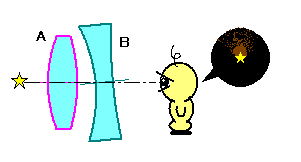 「像にアスがある」などと表現される。
「像にアスがある」などと表現される。
これが許容範囲を超えていると、不良品としてラインから弾かれ、修正部門へ回される。
不良品の修正方法の一つとして、俗に「玉回し」と呼ばれるものがある。
玉とはレンズのことである。
全部を分解して不具合の原因を突き止めるのは大変なので、とりあえず最前面のレンズ(A)を回してみるのである。
レンズAにも多少の製造誤差があるので、くるくる回してやると、レンズBの誤差を打ち消すような組み合わせが偶然見つかることある。
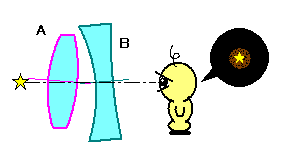
これで直れば、分解は最小限で済むので助かるのである。
ただ、これは「アスの相殺」であって、星像を取り巻くフレアは実は消えておらず、ただ均等になっただけだったりする。
それでも流れたフレアよりはずっとマシで、倍率を上げなければ十分だと判断されれば、合格となる。
これが調整機構を持たないカメラや双眼鏡での「調整」。
こう文章で書くと簡単そうに思えるが、実際には組立てのベテランの腕に頼った名人技であり、普通の人には無理とのこと。
この「玉回し」の話でピンと来た方もいたのでは?
そう、低倍率で良ければ、今回の望遠鏡のアスも同じ原理で直せるのではないかと考えたのである。
コマ収差の補正用に入れたバーローレンズを主鏡のアスを打ち消すためにも使うのである。
もっとも主鏡の傾きが尋常ではないので、バーローレンズを回すのではなく、意識して傾ける必要があるだろう。
次回はそのバーローレンズを傾ける方法を考える。
さて、どうなるかな?
30倍どころか、3倍でも厳しかったりして・・・