プリズム
プリズムを取り出してカビを拭く。これは,拭けば容易に落ちた。

コストダウン優先の製品なので,あらゆる点で手が抜かれ,コバ塗りなどもされていない。
そこでコバ塗りをしてみよう。
コバ塗り専用の塗料があるものの,我々には入手困難。でも身近に良い塗料がある。
書道用の墨を濃い目に作って塗るのだ。
 墨を摺るのは何世紀ぶりだろう・・・。
墨を摺るのは何世紀ぶりだろう・・・。
墨は水で拭けば簡単に取れるので,ハミ出しなど気にせず,ガンガン塗れる。
しかも乾燥すれば,レンズの拭き上げで使用するアルコールには溶け出さないと言う利点がある。

(ちなみにコバ塗りに墨を使ったのは,ドイツで,それが日本に伝わったらしい。)
苦労して拭き上げたプリズムは,手で触らないようピンセットで慎重に入れる。

バネをスライドさせて装着する。


対物レンズのクリーニング
対物レンズの裏面も強烈に汚い。
だが,対物レンズは鏡筒にカシメられており,取れない。
仕方がないので,割り箸の先にペーパーを巻き付け,クリーニング液を付けて拭く。

このようなアルコールでは落ちないような汚れには,富士フイルムのクリーニング液が効く。
参考:レンズのクリーニング

左:拭く前,右:拭き済
ただ,レンズ周辺は拭き残しが出るし,劣化したコートが部分的に剥がれたりして,新品同様とはならない。
自分の物を個人の責任で修理しているから気にもしないけど,有償修理を請負う人は,寿命が縮まる思いではないだろうか?
調 整
倒れ,軸出し,視度調整は,エバーライトと同じ手法である。
軸調整は平行器,視度調整は,視度望遠鏡を使えば検証出来るが,像倒れは,どうも
スッキリしない調整方法だ。
ここも光学的な治具を作りたくなってくる。
光軸調整ネジと像の動きを参考までに掲げよう。
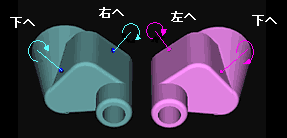
双眼鏡をバラすと,その光軸調整機構には,対物レンズをシフトする方式,プリズムをシフトする方式,接眼レンズをシフ
トする方式など,バ
リエーションが多いことに気付く。
上記の図は,プリズムをチルトさせる方式の双眼鏡の場合。
理屈は追い切れていないのだけど,実際に回してみた結果を書いてみた。
エバーライトの光軸調整で書いたように,眼幅を変えても光軸が出るように調整するのは容易では無い。
自分専用で良いならば,自分の眼幅での光軸調整に留める
妥協策も有りかと思う。
完 成
レンズ,プリズムはキレイにしたし,コバも塗ったし,内部も黒くした。
だから見え味がバッチリか,と言えば,そうではない。
諸悪の根元は,接眼レンズ。おかしな2枚玉形式なのが痛い。
周辺像が悪く,色収差が目立つのだ。
エバーライトで使われている平凡なケルナー式が,いかに偉大な発明品だったかを実感してしまう。
もっとも,昼間の景色を眺める分には,それなりに見える。
こんな廉価な双眼鏡でも肉眼より はるかに良く見えるのだから。
故障品の修理は,業者や製造メーカ-へ依頼するようお願いします。
参考文献
「ライカに追いつけ」(朝日ソノラマ),「双眼鏡 歴史と技術NO.27,83」(月 刊天文 中島隆氏),「スターウオッチング」(誠文堂新光社)
技術指導
井沢氏 他