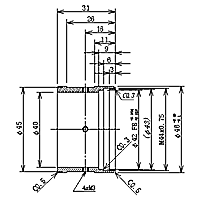
単純ミスが多いので図をよく確認
本機は,対物レンズを動かすことで焦点調整を行います。
そこで,対物セルにはPOM(*)を使います。
*ポリアセタール。摺動性に優れたエンプラ。「ジュラコン」,「デルリン」という商品名の方が有名。
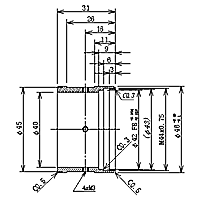
プラスチックは,しっかりチャック出来ず,加工中に外れやすいのが難点です。
そこで,丸棒にネジ穴を開け,旋盤の主軸を通したズンギリボルトで固定する方法を考えました。
 苦肉の策。チャック部分にはスリップ防止の紙
も
接着。
苦肉の策。チャック部分にはスリップ防止の紙
も
接着。 (1)
(1) (2)
(2) (3)
(3) (4)
(4)左から順に
(1) 外形を削る,(2) 対物レンズが入るよう内部をくり抜く,(3) 押え環と合うようネジを切
る,(4) 突っ切り(切断)
この時は,黒色のPOMが手に入らず,やむなく白色を使用。
あとで内面を黒く塗りますが,POMは塗料の付着性が悪いのが欠点です。
鏡筒はφ50とφ40のアクリルパイプを使用しています。
パイプの連結部分は,プラ板を丸めて接着し,旋盤で仕上げます。
 パイプは強くチャック出来ないため,「フタ」を仮接着し,センター押しを使
用。
パイプは強くチャック出来ないため,「フタ」を仮接着し,センター押しを使
用。
端面仕上げや内面切削は,この手法も使えないため,「フレ止め」というオプションを購入。


これを使っても,加工途中で脱落することが多く,ちょっとガッカリ。
視度調整範囲のスペックは,±3ディオプター以上。
誤差を考えると±4ディオプターは欲しいところ。
これは接眼レンズの移動距離が,±1mm程度になる計算です。

まず,接眼レンズがスライド出来る2重構造の枠を作ります。
視度調整リングのカム溝は,連続した穴を開け,ヤスリで仕上げます。

完成した視度調整部。

視度リングを回転させると,カム溝によってピンが前後に動き,内部の接眼レンズが移動します。
本体の部品がだいぶ揃ってきたので,仮組してみました。

仮調整し,試用します。
ファーストライトは,近所の風景。
「見えた〜\(^o^)/」と喜んでいるのも束の間,すぐに,いろいろな問題も見えてきます。(T_T)
内面反射が多く,コントラストが悪い,解像度が悪い,各部のバックラシが大きいなど・・・。
像が悪いのは,プリズムケースが精度不良で光軸が狂っているため。
内面反射も多く,新たに遮光環を設ける必要がありそうです。
 ジャンク部品の転輪が小さ
くて操作性がイ
マイチ。
ジャンク部品の転輪が小さ
くて操作性がイ
マイチ。本体が形になってきたので,これらの問題を修正しながら,外装カバーの検討に入ります。