 堂平山にて
堂平山にて傾斜
双眼鏡を改良する
Part.1 粘土で考える
気になる欠点
「空も地上も楽に見られる双眼鏡が欲しい」
ということで5年前に作ったのがこの傾斜接眼の双眼鏡である。(HE06)
たしかに地上用途に使うことは出来るようだ。
 堂平山にて
堂平山にて
しかし、地上用途だと完成度が高い市販の双眼鏡がライバルに
なるので、いろいろ分が悪い。
まず、内面反射が多いので日中はコントラストがイマイチである。
 夜、星を
見ている時は気にならないんだけどねえ・・・
夜、星を
見ている時は気にならないんだけどねえ・・・
この内面反射は製作当時も気になって植毛紙を貼ったりしたものの、不十分である。
 内面反射が多い
内面反射が多い FRPで苦労して作ったカバーも持ちにくいし、デザインも良
くない。

苦労して作ったセンターフォーカスの転輪も指が届きにくくて不便。
5年ぶりに平行器で測定してみると、軸ズレも許容量を超え、レンズも汚れてきたのでオーバーホールが必要だ。
それとずっと気持ち悪かった点がある。
製作時にピントが出ず、原因不明のまま筒を 5mm短くしたこと。
今回、ダイナメーターで対物レンズの焦点距離を逆算すると、業者が出していた値より 6mmほど短かったことが判明。
当時は公称値を疑わず、自分の設計のどこがおかしいのだろう?と散々悩んだものだった。
おかげで光路図まで「オーバーホール」である。(^_^;
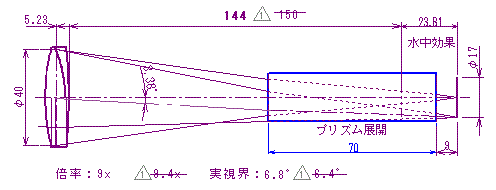 どうも天体機器
の公称値はあてにならない (`Д´)
どうも天体機器
の公称値はあてにならない (`Д´)
5年ぶりに謎が解明出来てスッキリ。スペックも少し変わってしまうが、却ってキリがいい(?)
このように色々と気になる点があるので、この双眼鏡をベース
に改良版を作ることにする。
カバーを考える
使いにくさはカバーの煮詰め不足に原因があろう。
カバーに関しては頭でいくら考えても実際に手で持ってみないと分からない。
そこでやはり粘土を使って検討することにする。
とは言っても、ベースとなる中味が既にあるので好き勝手な形状にすることも出来ない。
そこで、5年前と同様に 5mm厚のスチレンボードを積層して中味のモデルを作る。
 再び作った積
層モデル。捨てなきゃ良かった。
再び作った積
層モデル。捨てなきゃ良かった。 これに油粘土を盛って、形状を検討する。
粘土は 5年前に使った「楽しい油粘土」が残っていたのでそれを使う。
手が入るようにボディーは絞り込んだ方がいいな。

親指が当たるところ
は凹ませて・・・

結局、中央を絞り込んだ形がいいという結論に


色がツートンになっているのは、途中で粘土が足りなくなって 100円ショップで買ってきた油粘土を追加したため。
しかし、幾らボディーを絞っても真ん中にある転輪には指が届かないようだ。

5年前の手法だと、このまま粘土モデルを仕上げ → 石膏で
型取り → FRP
という風になる。
しかし、それではカバーの数値的なデータが無いため図面上で中味と重ねて詳細を詰めていく・・・ということが出来ない。
それでは 5年前の手作りカバーと大差ない。
今回は新しい製作方法を模索することにする。
(2010-8-17
掲載)